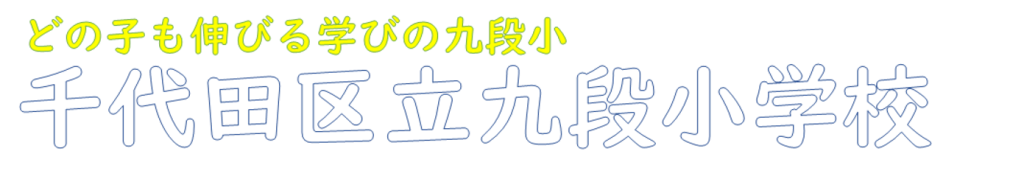教育の方針
教育目標
人権尊重の精神を基盤とし、国際的視野に立ち、自主性、創造性に満ちた児童を育てる人間教育を推進する。そのために、次の目標を設置する。
◎進んで学ぶ子 ○仲よく助け合う子 ○心も体もたくましい子
・自ら学ぶ意欲をもち続け、確かな学力を身に付け、主体的・対話的に課題を解決する資質や能力を育む。
・他者を思いやり、違いを認め合い、他者と協働し、自分を大切にする心をもち、生命や人権を尊重する豊かな心をもつ。
・変化の激しい社会の中でたくましく生き抜くための健康と体力を身に付け、何事にも積極的に取り組む意欲をもつ。
教育の概要
1.学校・地域の特色
人・自然・文化が調和された地域や家庭環境の中で本校は、転入者の多い特性を踏まえながら、家庭や地域との連携を深めた教育活動を推進していく。
2.教育目標達成のための基本方針
ア 人権教育を基本とし子どもの道徳性を培うとともに、健康で安心・安全に過ごす学校
① 子どもの人権を尊重し、体罰、虐待、暴力行為を根絶するため、千代田区の「いじめ防止基本方針」を踏まえ、教職員、児童、保護者、地域が連携し、子ども一人一人の心が安定する居場所をつくる。
② 他者を思いやり、人との関係をよりよく築く力を身に付けるため、全教育活動を通して人権教育や道徳教育を充実する。また、心の教育を推進して豊かな人間性を育むとともに、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を行い、早期解決を図る。
③ 子どもが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないために、児童の発達段階に合わせた生命(いのち)の安全教育に取り組む。
イ 主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善により、子どもに質の高い学びを実現する学校
①
国際教育を推進するために、言語活動や異文化理解を通して、自国を誇りに思い、他国を尊重し、異文化を受け入れ、積極的に関わろうとする資質・能力と豊かな人権感覚をもったグローバル人材を育成する。
②
「知識及び技能」の定着と「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の育成、新しい時代に必要となる資質・能力の育成と学習評価の充実を図るため、「九段スタイル」を実践する。
③
基礎的・基本的な知識や技能の確実な習得を図るため、教科担任制やティーム・ティーチング、習熟度別少人数指導、一人一台タブレット端末を利活用した個別最適な学びによる個に応じたきめ細かい指導を通して、確かな学力と体力を身に付ける。
④
全教育活動を通して、子ども一人一人の考えや意見が安心して表現できるようにするため、「九段スタイル」の取組と、「学びのスタンダード」の定着に家庭と連携して取り組み、子ども自らの学習意欲を高める。
⑤
子どもにとって授業が「できる」「分かる」「楽しい」と実感できるようにするため、週ごとの指導計画や個別の教育支援シート、人的支援を効果的に活用する。
⑥
自ら進んで心の健康と体力づくりに関わる子どもを育成するため、すいみんチェックカードや体力テストのデータ分析を基によりよい生活習慣の確立と体力の向上を図る。
ウ 地域、保護者とともに歩む学校
① 「九段ブランド(本校のよさと伝統)を極める」を合言葉に、子どもにとってよき思い出や成果を得るためによりよいもの(こと)を目指し、地域、保護者と連携・協働して、意図的、計画的、継続的な教育活動を積み重ねる。
②
社会に開かれた教育課程の実現を図るため、学校運営協議会や地域学校協働活動を活用し、地域との連携を深める。また、教育課程の達成状況と改善策を明確にするため、各学期の学校公開や学校だより、学校ホームページを通じて教育目標や教育活動を積極的に公開し、年2回の学校評価を行う。
③
子どもが自らの成長と自分のよさが実感できるようにするため、体育的行事や文化的学芸的行事、地域の教育力を活用した教育活動を実施する。
④
子どもの発達や学びの連続性に配慮した教育を行うために、保幼・小中一貫教育を推進する。また、幼児教育と小学校教育を円滑な接続を図るために、九段幼稚園と連携したスタートカリキュラムと英語によるコミュニケーション能力の一層の充実を図る。
⑤
保護者が子どものよさや課題に応じた指導や支援方法などを相談できる体制を構築するために、学校公開や個人面談、日常的な連絡等を通じて、積極的に情報を発信する。
⑥
持続可能な社会づくりにおいて課題解決に必要な7つの能力・態度を身に付けるためSDGsの取組をCES(千代田エコシステム)と関連させ、実践を通してSDGsに対する理解啓発を図る。
エ 組織の力で課題解決を図る学校
①
学校の教育目標を実現するため、子どもや地域の実態を明確にした教育課程を編成・実施・評価し、改善を図り、計画的・組織的にカリキュラム・マネジメントを推進する。
②
質の高い教育活動を推進するため、子どもの実態や地域の実情等を把握し、教科等横断的な学習指導の充実を図る。
③
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育をすすめるために、全教職員と保護者、関係諸機関が連携し、子ども一人一人を伸ばし育てる環境と合理的配慮、指導方法等についての理解を深める。
④
子どもが安心して学習に取り組めるようにするため、子どもの困り感と特別の教育課程や教育支援シートに基づき、個に応じた指導と支援を展開し、進捗状況を例月の校内特別支援教育委員会で確認する。必要に応じて、特別支援学校や特別支援学級設置校と連携する。
⑤
児童と教職員のウェルビーイングをより推進するため、学習指導の充実とより正確で丁寧な評価(通知表を年2回作成)、学校行事の精選、プラチナ休暇取得(学期中の計画的な年休取得)の奨励、人的支援の有効活用を図る。
オ 教職員が互いに学び合い、高め合う学校
①
教員は「授業で勝負をする」を合言葉にし、子ども一人一人がもつよさと可能性を伸ばすため、教員各自の専門性(強み)を生かし、「弱み」を克服する校内研究会の充実に努める。
②
質の高い教育を推進するため、年2回の学校評価を通じて、個々の課題と改善策を明確にする。
③
学習の効率化や働き方改革を図るため、生成AIの利活用を推進する。
3.指導の重点
1 各教科、特別の教科道徳、外国語・外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動
ア 各教科
○課題解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むために、1 単位時間の学習過程、板書やノート指導による思考の振り返り、ペア・グループ・全体での相互交流場面の設定、学習ルールの徹底を示した「九段スタイル」を推進する。
○基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図るために、学力調査や達成度調査の結果や日常の学習状況を的確に把握し、指導と評価のCAPDサイクルが一体化した授業を展開する。
○個別最適な学びや協働的な学びを充実させるため、一人一台タブレット端末やICTを効果的に活用した学習活動を行う。
○専門性の高い教科指導による教育の質の向上や学年組織を意識した対応のために、第5学年及び第6学年において教科担任制による指導の充実を図る。
○個に応じたきめ細かな指導のため、3年から6年の算数科で習熟度別による少人数指導の充実を図る。
○教科等横断的な学習の充実を図るために、「主体的・対話的で深い学び」の学習活動を意図的、計画的に年間指導計画に位置付ける。
○日常的な読書活動の充実を図るために、図書担当教諭を中心に読書週間を計画的に行い、読書アプリの活用を推進する。また、大妻女子大学の学生による読み聞かせ活動を通して、図書に親しむ時間を設定する。
○体育健康教育(体力向上、歯科指導、がん教育など)の充実を図るために、アスリートとの交流や企業との連携した取組を継続的に実施し、正しい理解と生活習慣の改善を図る。
イ 特別の教科 道徳
○命と心の教育を推進するため、全学年の重点を「自分も他の人も大切にする心の育成」とし、生命を尊重する心、思いやりのある心、心の豊かさや規範意識を育てるとともに、社会に貢献しようとする意欲を醸成し、よりよく生きるための道徳性を育てる。
○道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てるため、道徳教育推進教師が中心となり、道徳科の特質を正しく理解し、道徳科における指導と評価の一体化を図る。
○道徳科の授業の充実を図るため、心の教育コーディネーターや外部講師と連携する。
○外国語によるコミュニケーションの基礎となる資質・能力の育成と自国及び他国の言語や文化等の異文化理解を深めるため、子どもの発達段階に応じた意図的・計画的な体験的な活動を行うなど、外国語指導の充実を図り、HRT(T1)とALT(T2)が連携した授業を展開する。
○子どもの主体的な学びを促し、学習で得た「知識・技能」を多様な場面で活用する力を育成するために、教科横断的な視点に立った外国語・外国語活動の授業づくりを行う。
○より広い視野をもち、外国語で主体的・積極的なコミュニケーションを図る態度を育むため、5年と6年で東京グローバルゲートウェイ(TGG)での交流・体験活動を位置付け、国際教育の推進を図る。
○主体的に判断し、これまで獲得した知識・技能を生かして課題解決を図る思考力・判断力を育成するため、子どもの疑問や関心に基づき、自ら課題を見付け、体験的活動や調べ学習を行い、横断的・総合的な学習や探究的な学習を展開する。
○探究的な活動を充実させるために、見学やグループ学習などの学習形態の工夫、ゲストティーチャーや地域人材の活用など、子どもが人・こと・ものと関わる機会を意図的に設定する。その学習過程において、一人一台端末や情報通信ネットワークを適切かつ効果的に用い、情報活用能力を含めた情報リテラシーを育む。
○地域の伝統行事や文化など我が国の伝統文化への造詣と理解を深め、伝統文化を尊重する態度を培うために、専門性の高い人材や教育資源を活用する。
オ 特別活動
○自主的・実践的な態度を育むため、各教科等と関連付けた学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事等の計画と指導の充実を図る。また、様々な集団活動を通して、自己の課題を見いだし、その解決を図るために、よりよい人間関係の構築や集団生活の形成を図ろうとする態度を育てる。
○異年齢活動の中で、子どもが互いを思いやり、集団行動の望ましい在り方を学ぶために、縦割り班活動「フレンズ班」を通して、互いを尊重し合う好ましい人間関係を育む。また、児童会活動やクラブ活動、集会活動も含め、上級生が下級生の手本となるように働き掛ける。
○子どもの発達段階に応じて、思いやりの心や社会性を育むために、異学年間および九段幼稚園及び近隣の保育園等との継続的な交流を充実し、互いに尊重し合える人間関係を築き、成就感と達成感を得る。
○学ぶことと自分の将来とのつながりを考え、社会的・職業的自立に向けて基盤となる資質・能力を育むため、各教科などの特質に応じて、キャリア教育を推進する。
○子ども一人一人が、学ぶこと、働くこと、生きることについて考え、多様な他者と協働しながら、自分の生き方をつくろうとする力を身に付けるために、学級活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」の授業を毎学期1時間以上は設定する。また、自己有用感や自己肯定感、成就感を実感できるよう、キャリア・パスポートを工夫し活用する。
2 特色ある教育活動
〇「地域を支える人づくり」「地域とともに育つ学校づくり」を推進するため、「ちよだ楽」に取り組み、千代田区のよさを積極的に発信する。
① 俳句の学習を通じて、日本の伝統文化に慣れ親しみ、句会を通じて豊かな人間関係を築く。
【全学年】
② 循環型ビオトープを利活用し、都会における生態系を学び、自然の営みを学ぶ。【全学年】
③ 英語の授業の充実と東京グローバルゲートウェイ(TGG)の利活用により、国際感覚を養
い、コミュニケーションの基礎を養う。【5・6年】
④ 神幸祭・山王祭の歴史と伝統、取組を学び、地域への愛着を高め、地域の一員としての自覚をもつ。【3・4年】
⑤ 屋上菜園を利活用し、野菜づくりの体験や栽培、収穫を通じて食ヘの興味や関心を高める。
【全学年】
○外国語に親しみ、言語や文化への興味や関心を高め、豊かな人間関係の醸成と就学前からのコミュニケーション能力を充実するために、九段幼稚園の園児と本校の子どもたちとの交流プログラム「えいごでなかよし」を実践する。※幼稚園では「えいごであそぼう」と呼称する。
○情操教育や伝統文化の素晴らしさにふれさせるとともに、学校代表の意識と地域等の連携・協働を図るため、九段プラネッツや九段囃子の活動を充実させ、継承・発展する。
○「走・跳・投」の技能を高め、運動に親しみ、運動する楽しさを実感するため、キッズアスレティクスによるアスリートや投げ方教室の講師から専門的な指導や助言を受け、自己の伸長を体感する。
3 生活指導・進路指導
ア 生活指導
○子ども一人一人の思いを受け止め、児童理解をより深めるため、全ての学校生活において全教職員で児童を指導、支援し、必要に応じて保護者や関係諸機関と連携する。
○言葉づかいや姿勢等の基本的な生活・学習規律の定着を図るため、「九段スタンダード」を活用する。
○いじめ0や不登校0、その他の問題行動を未然に防ぎ、組織的な解決を図るために、学校いじめ防止基本方針のもと、全校の共通理解を基盤として生活指導全体会・特別支援校内委員会・特別支援個別検討会・個人面談・ふれあい月間の充実、のびのびルームの活用を図る。
○思いやりの気持ちと自らの特性に気付くため、生活アンケートの活用やスクールカウンセラーによる4、5、6年全員面接、フレンドシップサポート事業を計画的に実施し、自尊感情を育む。
○生活安全や交通安全、防災教育において、子ども自らが自身の命を守る行動の大切さや安全を意識して生活するため、毎月の安全指導や安全学習、避難訓練の実施内容を工夫する。
○心と体の健康に関する知識や技能を身に付け、学んだことを実生活の中に生かせるようにするため、保健の学習や給食指導、保健指導の充実を図る。
〇自殺予防や生命尊重の理解啓発を図るため、SOSの出し方に関する指導を5年生以上の児童を対象に長期休業前に実施する。また、各学年の発達段階に応じて様々な困難・ストレスへの対処方法を学ぶ授業を実施する。
○家庭・地域と連携し、子どもの安全確保や健全育成を図るため、子どもの発達段階に応じてセーフティ教室を実施する。また、情報モラル教育を推進し、SNS九段ルールの徹底を通じて、すべての子どもが安心して生活できるようにする。
イ 進路指導
○自己理解を深め、主体的に行動し、自分のよさや可能性に気付き、よりよく生きていこうとする態度や能力を育てるために、キャリア・パスポートを活用し、自分を振り返りながら、他者との関わりを大切にした教育活動を推進する。
○子どもが自身のよさを自覚し、将来への夢や希望をもち、生涯にわたって学び続けることの価値に気付くよう、キャリア教育の充実を図る。
○自己の生き方を考え、社会に貢献しようする態度や意欲を育てるために、地域のよさに気付き、よさを発信する「ちよだ楽」に取り組み、地域の一員としてよりよい町にしていこうという心情と態度を育む。
○高学年は多様な進路について的確な選択やその判断力を培うため、自己の将来に向けた希望をもち、志を抱ける場を意図的に設定する。
通級による指導(情緒障害等)の教育目標
1 教育目標
障害による学習面、生活面における困難さを改善・克服し、自主性、創造性に満ちた人間教
育を推進する。
◎進んで学ぶ子 ○仲よく助け合う子 ○心も体もたくましい子
・自己の特性を理解し、自ら学ぶ意欲をもち続け、確かな学力を身に付け、主体的・対話的に課題を解決する資質や能力を育む。
・小集団指導を通して、コミュニケーションに必要な知識や技能を身に付け、他者を思いやり、互いのよさと違いを認め合い、自分を大切にする心をもち、生命や人権を尊重する豊 かな心をもつ。
2 教育目標を達成するための基本方針
(1)授業が「できる」「分かる」「楽しい」と子どもが実感できるようにするため、週ごとの指導計画や教育支援シート、人的支援を効果的に利活用する。
(2)子どもが安心して学習に取り組めるようにするため、子どもの困り感の解消と特性に応じた教育支援シートを作成し、個に応じた指導と支援を展開する。また、例月の校内特別支援教育委員会で指導の成果と課題を確認する。
(3)人とよりよい関係を築く力を身に付けるために、指導形態を工夫し、他者を思いやり、互いのよさと違いを認め合う経験を重ねることで自己有用感と自己肯定感を高める。
(4)「学びのスタンダード」を基軸に、規範意識、学習規律、生活規律及び社会性を育むため、自己理解と相互理解を大切にし、あいさつ、礼儀、言葉遣い等がしっかりと身に付くようにする。
(5)子どもの困り感や特性に関する理解を深めるために、学級担任、巡回アドバイザー、講師(特別支援教育)、特別支援教育専門員、特別支援教室専門員等と連携を図る。また、適切な情報収集や指導と評価、支援に努める。
(6)児童一人一人の障害の状態や特性に応じて教育支援シートを作成及び活用し、個別指導や小集団指導を組み合わせて効果的に指導する。
(7)在籍学級における通級している子どもの状況を把握し、指導と支援に役立てるため、行動観察や学級内支援等を行う。
(8)指導と支援の充実を図るため、定期的に打合せやケース会を行い、個別指導や小集団指導の成果と課題、改善策について共有する。
(9)保護者が子どものよさや課題に応じた指導や支援方法等を相談できるようにするため、各学期の学校公開や年2回の個人面談、指導の記録等を通じて、積極的に連携する。
3 指導の重点
(1)子ども一人一人の障害の状態や特性に応じた指導と支援、評価を行うため、自立活動の6区分27項目の指導内容から必要とする指導項目を選択し、教育支援シートを作成する。さらに学ぶことの楽しさを実感するとともに基礎的・基本的な知識や技能を身に付け、学習に主体的に取り組む態度を育む。
(2)身に付けたことが在籍学級で活用できるようにするため、個に応じた教材や支援ツール、IC
T機器を利活用し、指導する。
(3)体験的で具体的な方法を身に付ける指導を行うため、個別指導や小集団指導の場面において、ロールプレイング等を行う。
(4)各教科等における自己のよさと課題を理解し、改善に結び付く学習方法を身に付けるため、障害の特性に応じた教科等の学習内容を取り扱いながら、自立活動を行う。
(5)集団のよさを生かしたグループによる指導を行うため、課題別の小集団を編成する。
(6)子ども同士の様々な交流を通して、コミュニケーション能力及び豊かな人間関係を築く個に応じたスキルを身に付けるため、時と場、相手に適切に反応する言語的・非言語的な対人行動の習得練習を重視する。また、友達と協力して活動し、成果を共有したり、肯定的に評価されたりする経験の機会を増やす。
(7)日常生活に必要な基本動作を習得し、生活の中で適切な身体の動きを意識できるようにするため、コオーディネーショントレーニングを活用する機会を設定する。
(8)外国語に慣れ親しみ、言語や文化への興味や関心を高め、豊かな人間関係の醸成とコミュニケーション能力を充実させるため、挨拶などで英語を活用する機会を設定する。
4 その他の配慮事項
(1)個に応じたより効果的な指導を展開するため、アセスメントに基づいた教育支援シートを作成する。定期的に指導目標・内容・手だてを検討し、終了目標に向けた指導の充実を図る。
(2)子どもの困り感や特性に応じた適切な指導を行うため、教育支援シートを活用しながら、在籍学級担任、通級担当教員、巡回アドバイザー、スクールカウンセラー、保護者等と成果と課題の解決に向けた具体的な手だて等の共通理解を図る。また、関係諸機関との連携に努め、組織的、計画的、継続的な指導を行う。
(3)特別支援教育校内委員会の実施は月1回を基本とし、緊急時には臨時に設定する。また週1回の生活指導夕会において情報共有を行い指導体制を整える。